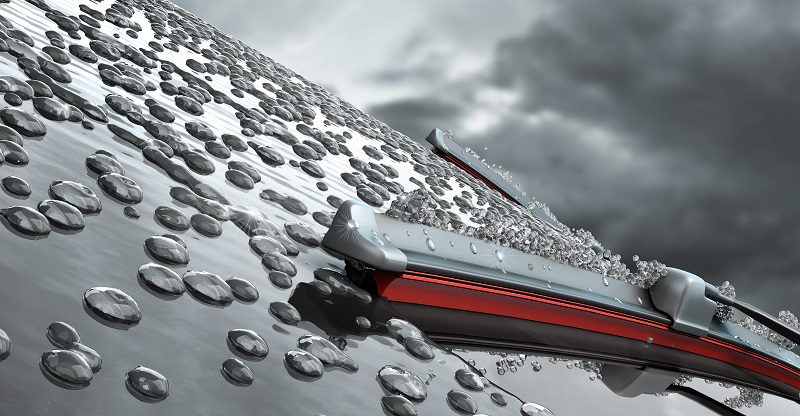事業目的で物件を購入するときの融資で、ぜひ利用を検討したいのが信用保証制度。
今回はその中身に迫ってみよう。
信用保証制度とは、物件の購入資金を融資で調達するときに信用保証協会を保証人に立てるシステム。信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者の借り入れを後押しするために作られた公的機関。
つまりこの制度は、公的な債務保証を受けることで金融機関からの融資をスムーズに進めるというものだ。
この制度を使うときの流れはおおむね以下のとおり。
1.金融機関に融資を申し込む
2.金融機関に信用保証制度の利用を依頼する
3.信用保証協会向けの申込書類を作成する
4.3の書類を金融機関経由で提出する
5.金融機関と信用保証協会が同時進行で審査する
6.審査通過、金融機関が融資の実行
申込者(=債務者)から見てお金を返済する相手(=債権者)は、あくまで金融機関。
信用保証協会は保証人という立ち位置だ。
では、信用保証制度に適するのはどんな場面だろう。
創業したて、もしくはこれから創業するというとき、営業実績が少ないため融資の可否を判断する材料も限られる。金融機関にしてみれば応援したくてもその決断がしづらい。そうした状況で、信用保証協会が債務保証してくれることになれば、融資を前向きに進められるというわけだ。
この制度の利用には保証料という追加費用がかかる。それを差し引いても、これから本格的に事業を起こす、もしくはこれまでの経験を生かして新天地で事業を始める人には強力な味方なのだ。
次に押さえておきたいのが審査のポイント。信用保証協会は審査の際、何を重視するのだろう。
実は協会の審査基準はベールに包まれており、はっきりしたことはいえないのだが一般的に次のとおりだとされている。
①事業計画の実現可能性
②事業計画の具体性
③融資の返済可能性
④申込者の信頼性
無理のない現実的な計画が立てられているか、順調に推移するための計画が細部まで詰められているか、収益に対して返済比率は適正か、また申込者は信頼に値する人かどうか、といった点が重要視されるようだ。
スケジュールはすべて終わるまで1~2か月かかるとみておこう。
金融機関と保証協会担当者の関係が緊密であれば審査は進みやすくなる。
保証協会から見て上記条件に不足がある、あるいは申込者の財務背景に問題がある、物件の担保価値が足りないといった場合に、金融機関が消極的になると審査は長引く傾向にある。
成功の鍵は、
①丁寧に事業計画書を作成すること(信用保証協会の書式は決まっている)
②金融機関の担当者といい関係を作ること
といえる。申込者が信用保証協会と直接やり取りすることは基本的にない。金融機関担当者が間で動いてくれる。その担当者がモチベーション高く仕事してくれるよう、各段階で積極的に協力しよう。
金融機関にとって、信用保証協会が絡む融資は取り分が減るので本来あまりやりたくない仕事だ。
そこをうまく乗せて円滑に進行させていきたい。
成功をお祈りします!