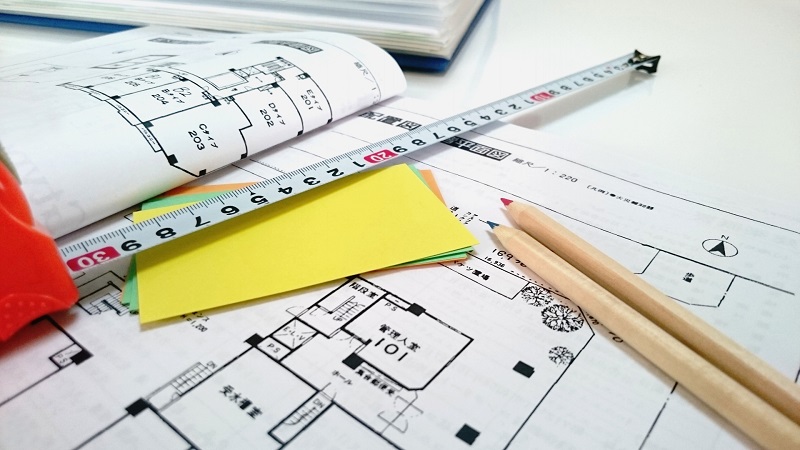今回は介護のお話です。
老いは誰にも等しく訪れ、人によっては寝起きや食事を自分で行うことが困難になります。
そんなときお世話になるのが介護保険の制度です。
介護保険は、21世紀の超高齢社会が抱える介護問題を、社会全体で解決する目的から生まれました。
この制度は、40歳以上の要介護者を支えるだけでなく、老老介護の世帯、単身高齢者、認知症高齢者をサポートする役割も果たしています。
介護保険の被保険者かつ介助が必要と認められる人であれば、サービスを受けることができます。
では、サービスを受けたいとき、何から始めればいいのでしょうか。
1.近くの窓口、支援センターなどに相談する
まずは、市区町村の支援センターに相談しましょう。
役所に聞けば、そのセンターや窓口の連絡先を教えてもらえます。
担当地区で分かれており、サービスを受けたい人が住んでいる家を基準にして窓口を選びます。
予約なしで行ける場合もありますが、まずは電話やFAXで事前に日時を尋ねてみましょう。
2.介護保険申請書を提出する
支援センターでは、要介護、要支援といった区分の目安、在宅で受けられるサービス、施設に通って利用できるサービスなどの説明があります。
「要介護」に当てはまるのは、日常生活で誰かの助けを必要とする人です。サービスを受けながら、少しでも自立した生活に近づけるよう、身体機能の維持、改善を目指します。
介護のレベルが軽いほうから要介護1~5の5段階に分かれます。
「要支援」に当てはまるのは、日常生活の一部で誰かの助けをいくらか必要とする人です。サービスを受けることで状態の悪化を抑えながら、自立した生活の維持を目指します。
支援のレベルが軽いほうから要支援1~2の2段階に分かれます。
ただ、相談の段階では、どのクラスに当てはまるのかわかりません。
そこで「介護保険申請書」を記入、提出します。
介護保険の利用者(被保険者)の情報、過去6か月間の医療機関入院歴や主治医の情報などをここで書きます。利用者本人が相談、記入困難な場合は、家族の誰かが代わりに行くことができます。
窓口では介護用ベッドや歩行器、車いすなどさまざまな介護用品についても情報を教えてもらえます。
「えっ? この用具がこんな費用で借りられるの!?」
と飛び上がるくらい、値段の安い物もあります。
介護にはお金がかかると考えがちですが、いざ現実を知ると、なるほど保険制度は相互扶助の精神で成り立っているのだなと、感謝の気持ちがこみ上げます。
3.調査員が家や病院を訪問
市区町村から依頼を受けた調査員が、利用者の家、入院中の病院などを訪ね、本人の様子を調べます。
寝返り、起き上がり、歩行、視力・聴力など74項目を調査し、判定の基礎資料にします。
また、家の内部、環境を見てもらうことで、介護のために必要な手直し、道具、家具も知ることができます。
4.認定がおりる
申請日から原則30日以内に要介護または要支援の認定がおります。
サービス開始は基本的に認定がおりてからなのですが、認定に先立って受けることもできます。
想像より認定レベルが低かった場合は、費用面でプラス負担になるかもしれません。その点は注意が必要です。
いかがでしょうか。
思ったよりスムーズですよね。
家族の介護が発生しそうなとき、まずは勇気を出して一歩踏み出してみましょう。